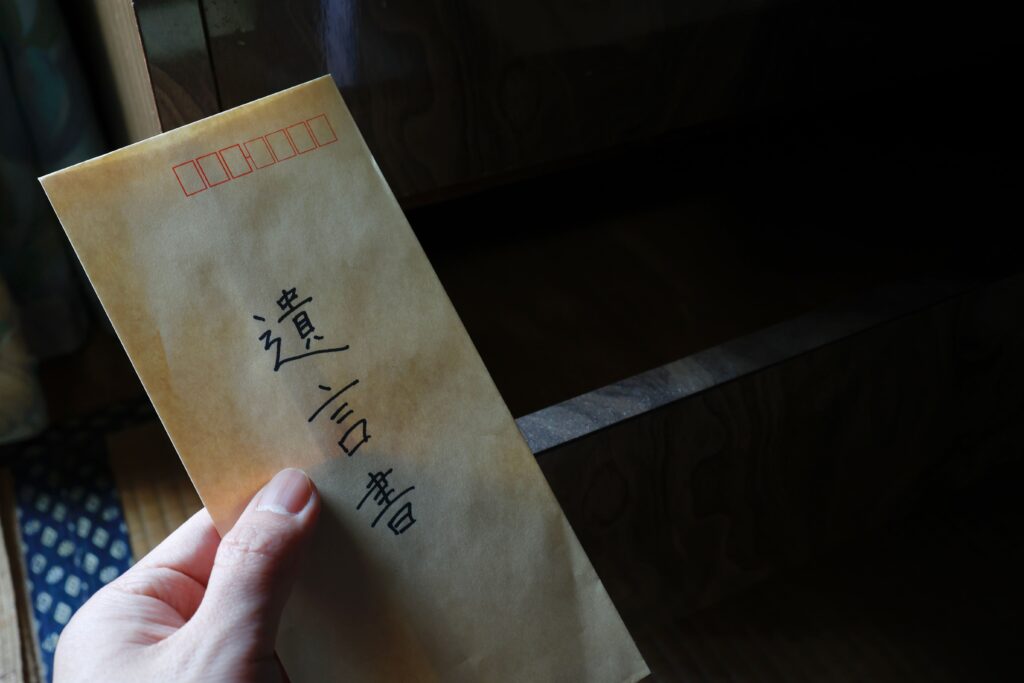遺言内容や生前贈与によって、相続が不平等になることがあります。そんなときは、遺留分侵害額請求を行うことで、相続人に認められる最低限の相続取り分を確保できるようになります。今回は「相続で不平等な状況を解消したい」という方に向けて、遺留分の制度と遺留分侵害額請求の方法を解説します。
遺留分とは?遺留分侵害額請求もあわせて解説!
同じ家族でも、遺言書の内容次第で受け取れる遺産の金額や内容が変わってしまいます。納得がいかないまま相続を進めることがないよう、遺留分と遺留分侵害額請求について知っておくとよいでしょう。遺留分とは
遺言書には故人の最終的な意思が反映されるため、その内容によっては相続人の取得分が大きく偏ることがあります。たとえば「全財産を長男に相続させる」といった記載があれば、ほかの子どもは一切財産を受け取れなくなります。また、被相続人が生前に多くの財産を特定の家族へ贈与していた場合も、結果として受け取れる遺産に著しい不公平が生じることがあります。遺言書や贈与が有効である限り、基本的にはその内容に従って遺産が承継されるため、相続人の間で納得できないと感じるケースも少なくありません。
このような不公平を一定の範囲の親族内で調整するために設けられているのが「遺留分」という制度です。遺留分は、法律で定められた特定の相続人が最低限保証される取り分であり、遺言の内容にかかわらず確保できる権利です。
対象となるのは配偶者や子ども、孫などの直系卑属、あるいは父母や祖父母などの直系尊属に限られています。兄弟姉妹には遺留分が認められていない点が制度上の大きな特徴です。遺留分が侵害されている場合、相続人は遺留分相当額の金銭を請求することができます。
遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権は、どれほど偏った遺言があったとしても、法律が保障する最低限の財産を確保できる重要な手段です。遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されていると分かった場合、相続人は遺留分侵害額請求権を行使することで、不足分に相当する金銭の支払いを求めることができます。たとえば長男が遺産の全てを取得する遺言があったとしても、次男や長女には遺留分が認められているため、長男に対して金銭の支払いを求めることが可能になります。ただし、遺言の修正を求めたり、相続財産そのものを返還してもらったりする制度ではありません。
金銭の請求を通じて実質的な公平を図ることができるものです。また、遺留分は法定相続分の半分を基本としています。
たとえば、配偶者と子どもが相続人である場合、配偶者は相続財産の4分の1、子どもは人数に応じて等分された8分の1ずつが遺留分となります。遺産が4,000万円の場合、配偶者は1,000万円、子どもは1人あたり500万円が遺留分として保障されることになります。
相続人が直系尊属のみのケースでは、遺留分が法定相続分の3分の1に引き下げられ、兄弟姉妹には遺留分が発生しません。こうした割合は請求可能額を計算する際の基礎となります。
遺留分侵害額請求権の手続きの流れ
遺留分の請求をしたいときは、下記のような手続きを行う必要があります。相手と協議する
遺留分が侵害されていると判断したら、まずは侵害している相手と協議し、支払いについて合意できるかどうかを話し合います。協議が円滑に進む場合は、この段階で解決できることも少なくありません。合意書を作成する
協議で合意に至った場合には、金額や支払い方法、支払い期日などの条件を明確にした合意書を作成します。後の紛争を予防するためにも、合意内容は必ず書面にして双方が署名押印し、保管しておくことが重要です。合意できない場合は内容証明郵便で請求する
話し合いがまとまらない場合には、正式な請求として内容証明郵便で遺留分侵害額を請求します。請求理由や支払い期限を明記することで、相手に対して公式な意思表示を行うとともに、紛争になった際の証拠として機能します。家事調停を申し立てる
内容証明郵便を送っても解決しない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。調停委員が中立的な立場で双方の主張を聞きながら調整を試みるため、当事者間だけの話し合いよりも合意にいたりやすい傾向があります。合意ができない場合は裁判での手続きへ
調停で合意できなければ、訴訟に移行します。請求額によって簡易裁判所または地方裁判所が管轄となり、証拠や法的主張を体系的に整理して争うことになります。訴訟手続きは専門性が高いため、弁護士の関与が有益です。遺留分侵害額請求には時効がある?
遺留分侵害額請求権には民法1048条で定められた消滅時効があり、一定期間を過ぎてしまうと権利が消滅して請求ができなくなります。そのため、相続が発生した場合には早めに状況を確認し、必要な手続きを進めなければなりません。遺留分侵害額請求の期限について
遺留分侵害額請求には「1年」と「10年」の2つの期限があり、それぞれ性質が異なります。まず、被相続人が死亡した事実と、遺言書や生前贈与によって遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に請求しなければ、消滅時効によって権利がなくなってしまいます。この1年の期間は消滅時効にあたり、一定の方法をとることで時効の進行を止めることが可能です。一方で、相続開始から10年が経過した場合には、遺留分侵害を知っていたかどうかに関係なく請求権が必ず消滅します。この10年の期間は除斥期間と呼ばれ、中断や停止が認められていない点が特徴です。
時効を止める方法
1年の時効を止める方法としては、相手方に対して遺留分侵害額の支払いを請求する意思表示を行う必要があります。口頭での請求でも効果はありますが、後日の証明のためには内容証明郵便で通知しておくことが望ましいです。また、裁判所に調停や訴訟を申し立てた場合にも時効の進行は止まります。この際、遺言書や検認調書謄本、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、相続人全員の戸籍、相続関係を示す相続関係説明図、そして遺産の内容を確認できる不動産登記事項証明書や預金通帳の写しなどが必要になります。
生前贈与が関係する場合には、その証拠となる契約書や登記記録等も重要な資料です。遺留分侵害額請求には期間制限があるため、書類準備は可能な限り早く進める必要があります。判決で遺留分侵害額の支払いが確定した場合には、判決確定から新たに10年の時効が進行する点も注意しましょう。